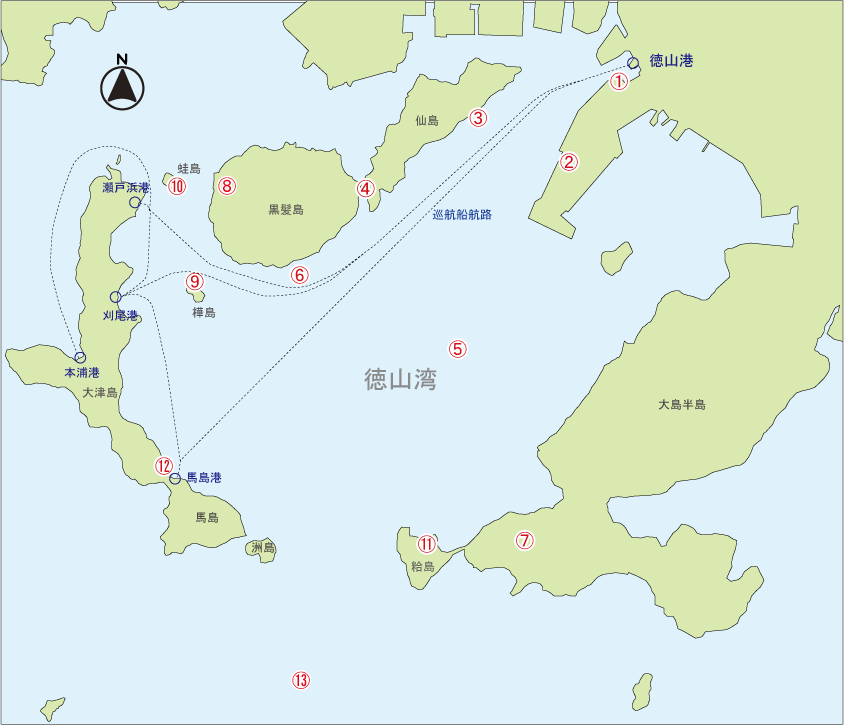|
 |
 |
| ①東浜崎の石灯台 |
②ガントリークレーン群 |
③海軍御用水槽 |
古くから天然の良港として栄えた徳山港のシンボルとして、その役割を果たしたのがこの灯台です。明治26年に、当時の海運会社「共栄社」の代表によって建立されたこの灯台は、ランプによって点灯していました。
平成14年3月に、船から一番よく 見える現在の位置に移転されました。なお、後方を走るのはフェリー新大津島丸です。 |
周南コンビナートの物流を支える徳山下松港は、吃水の深い船舶が出入できる港、又は外国船舶が常時出入する特定港湾に指定されています。
その船からの荷揚げに欠かせないのかガントリークレーン。巡航船からは大型の施設が4基確認でき、船上夜景ツアーでの見学コースには欠かせないものとなっています。 |
仙島周辺に設置してあった水を溜める槽。終戦まで、徳山港は軍港に準ずる要港の指定を受け、多くの艦船が入港していました。
そうした船舶に、水を補給するために造られた水槽は5基、確認されていますが、船からは4基確認できます。ただし、距離が離れているため、なかなか見つけにくいようです。(画像、黒っぽい中央の4角形の構造物)。 |
| |
|
|
 |
 |
 |
| ④二つの島を結ぶ干渡(ひと) |
⑤二つの灯浮標の海底で |
⑥大きな岩場の筏岩 |
仙島と黒髪島間は干渡と呼ばれる場所で繋がっています。戦時中、徳山港は要港であることから、港内での漁業等は制限を受けていました。そのため、湾内では自由に行動できる回天の搭乗員たちにとっては、絶好のアサリの捕獲場所であったようで、そうした彼らの証言が残っています。
なお、後方のタンク等は海を隔てた市街地側の工場施設です。 |
大島半島の石油タンクの前方に見える赤と緑の灯浮標。実はこの付近の海底は、人間魚雷「回天」の発案者で、大津島基地が開隊した時から指導官として回天に乗っていた黒木博司大尉が、訓練指導中に着底事故を起こした場所になります。
その後、救助が間に合わず、黒木大尉はこの場所で回天最初の殉職者となられました。 |
黒髪島南側に浮かぶ筏岩では、渡し船を利用して釣りを楽しむ人を見かけることがあります。
また、この海域では、春先に餌のイワシを追いかけて湾内に入ってくるスナメリと出くわすことがあります。運が良ければ、複数匹の群れで泳ぐスナメリを巡航船上からも見つけることができます。 |
| |
|
|
 |
 |
 |
| ⑦徳山湾のランドマーク |
⑧徳山みかげ採石場 |
⑨樺島での「回天」訓練 |
徳山港の入口になる大島半島の南端の小高い山の上に立つ煙突は、徳山湾入口を示すランドマークとなっています。
この煙突は、日本金属(株)徳山精錬所が亜鉛の製錬を行うために建設したもので、高さは72m、使用されているレンガの数は100万個を数えます。なお付近には、小さなレンガ造りの煙突も立っています。 |
花こう岩の一種で、墓石などにも使われている御影石。その良質なものが産出される場所が黒髪島にあります。ここでとれた御影石は「徳山みかげ」と呼ばれ、大正6年の国会議事堂の建設の際にも使われています。
なお大津島でも、良質な花こう岩が産出されており、大阪城の築城の際、その石垣に98個使われたという記録が残っています。 |
日本国内の海岸のがけなどに穴を掘って「回天」を隠し、敵艦船が近づいてきたら「回天」を出撃させる基地回天隊。
この隊は、全国に16か所設置される計画でしたが、実際に造られたのは11か所でした。
本土決戦に備えて設置された、その基地からの出撃を想定した事前訓練が、樺島の砂浜で行われていました。 |
| |
|
|
 |
 |
 |
| ⑩この島の名称は |
⑪粭島からフグ延縄漁が
|
⑫海から見える回天記念館 |
大津島と黒髪島の間に浮かぶ小さな無人島である蛙島。その名前の由来は、島の形がカエルに似ているからというものです。
巡航船から見てもなんとなくその形が連想できますが、市街地側から見たほうがよりリアルにカエルのシルエットが浮かんできます。 |
山口県沖の周防灘はフグの絶好の生息地として、古くからフグ漁が行われていました。このフグは強い歯を持っているため、通常の仕掛けでは噛み切られてしまいます。そのため、金属を使用した特殊な仕掛けを考案したのが粭島に住んでいた高松伊予作さんをはじめとした漁師の方々でした。
なお、前方を走るのはフェリー新大津島です。 |
馬島港に到着するという巡航船内にアナウンスが流れるころ、右舷側の小高い丘の上に見えてくるのが回天記念館です。
この場所には、もともとは馬島小学校がありましたが、学校の移設に伴い回天記念館が、昭和43年に整備されたのでした。
開館日には国旗が掲揚されていますので、たやすく場所を確認することができます。 |
| |
|
|
 |
|
|
| ⑬戦艦大和の最後の停泊地 |
|
|
昭和20年4月6日、日本海軍が世界に誇った戦艦大和が沖縄に水上特攻に向かいましたが、その日まで停泊していた場所は、粭島(画像左端)南西約1,500m沖の海上でした。
当時、徳山にあった第三燃料廠で燃料を搭載して当日、午後、ここから出撃して行きました。なお、残念ながら停泊場所を示す目印となるものはありません。 |
|
|
.gif)
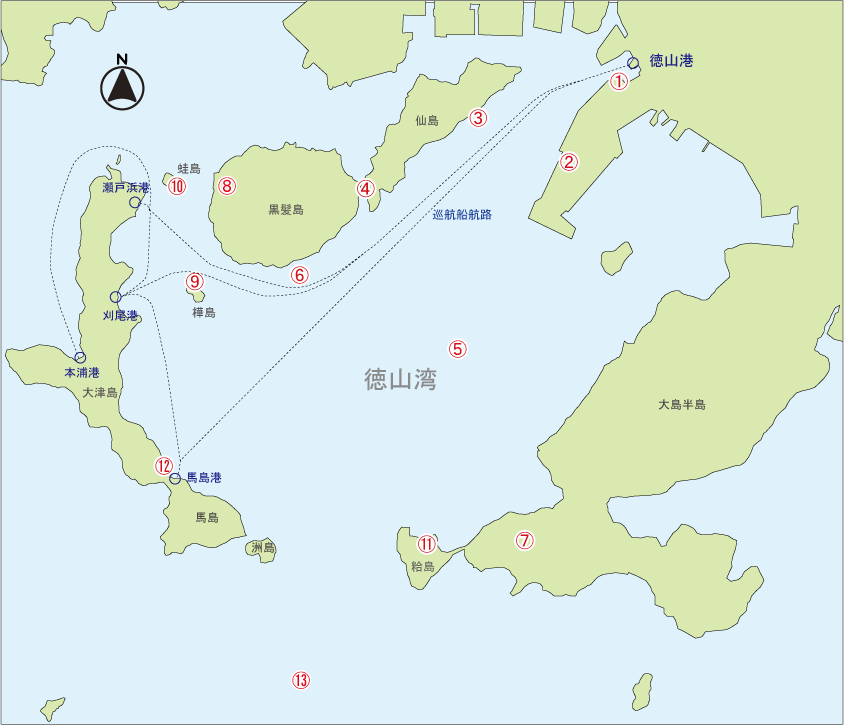
.gif)